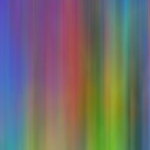コンセプトに必要なものは何か。それは「見通し」のよさに尽きるだろう。趣旨が明快であること、論旨が直截的であること、そして具象化による可視性の高さが条件となる。いわば「太く短く」ということだ。
最も避けるべきは、あれもこれもと欲張ることで総花的になり、あいまいさに主旨が埋もれてしまうことだ。
これを本質などと言えば、聞こえはいいが、一歩間違えると絶対的な位置づけは盲目を招く。ゆえにコンセプトたるものは、できあがったものではなく、つくりこんでいくものとの認識が妥当だろう。出発点ではアウトラインを示し、想起させるだけでいい。その中空のものに中身を詰め込んでいくのがプロセスだ。
さらに言えば、そのプロセス次第で、初期設定のアウトラインはある程度の揺らぎを吸収できるくらいの緩さが望ましい。それがむしろ乱れではなく成長のあかしなのだ。
コンセプトの由来は、ラテン語の「con(しっかりと)+capere(つかまえる)」なのだそうです。 いうまでもなくコンセプトは考える行為の肝であり、料理にたとえるなら調理にあたります。
情報源: アイデアは天才でなくても生み出せる。考えるための基本フレーム「リボン思考」とは? | ライフハッカー[日本版]
More from my site
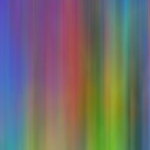 ストラテジック・エッジ 戦略水準としてみることのできる「安定的」「反応的」そして「先行的」、さらには「探究的」「創造的」の言葉は、環境適応を実現していくための「戦略の推進力」をとして理解していくことが重要といえます。
戦略水準1から3の「安定的」「反応的」「先行的」は、主として現在の事業領域を深耕しながら、さらに競争優位性を高めていくかが問われます。
これは「競争経営」の戦略概念がその中心と […]
ストラテジック・エッジ 戦略水準としてみることのできる「安定的」「反応的」そして「先行的」、さらには「探究的」「創造的」の言葉は、環境適応を実現していくための「戦略の推進力」をとして理解していくことが重要といえます。
戦略水準1から3の「安定的」「反応的」「先行的」は、主として現在の事業領域を深耕しながら、さらに競争優位性を高めていくかが問われます。
これは「競争経営」の戦略概念がその中心と […] 八方美人は刺さらない 希少性の時代から潤沢性の時代へと移り変わったことは、アプローチも相応に異なるという意味である。
需要と供給、その均衡や最大化というイメージは、旧来のグロスでのものの捉え方を引きずっている。予定調和的というか、線形思考というか。では、こうした前提自体を突き崩していくにはどうするか。どう満たすかという前提条件から、満たされた状況をどう打ち消すかという前提への転換だ。足し算思 […]
八方美人は刺さらない 希少性の時代から潤沢性の時代へと移り変わったことは、アプローチも相応に異なるという意味である。
需要と供給、その均衡や最大化というイメージは、旧来のグロスでのものの捉え方を引きずっている。予定調和的というか、線形思考というか。では、こうした前提自体を突き崩していくにはどうするか。どう満たすかという前提条件から、満たされた状況をどう打ち消すかという前提への転換だ。足し算思 […] 戦略は未来創造にある ボストン・コンサルティング・グループが、新たな戦略フレームワークを紹介した。この内容は、書籍「戦略にこそ『戦略』が必要だー正しいアプローチを選び、実行する」(2016.2.15)にその基本的な考え方を示している。この戦略アプローチは著書の一人でもあるマーティン・リーブス氏が2011年のHBRに「適応力戦略」アダブティブ(適応型)戦略として発表したものが基本となりそれとほぼ同様 […]
戦略は未来創造にある ボストン・コンサルティング・グループが、新たな戦略フレームワークを紹介した。この内容は、書籍「戦略にこそ『戦略』が必要だー正しいアプローチを選び、実行する」(2016.2.15)にその基本的な考え方を示している。この戦略アプローチは著書の一人でもあるマーティン・リーブス氏が2011年のHBRに「適応力戦略」アダブティブ(適応型)戦略として発表したものが基本となりそれとほぼ同様 […]