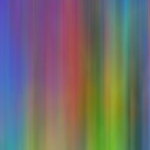科学万能の時代にあっては、感情などというあいまいなものは一段低くみられる傾向にあった。しかし、わかりやすい差別化が一巡した時代にあっては、あいまいという一見ネガティブな特性がかえって意味をもってくる。
リアリティとは実物としてそれがあるだけの話ではない。そこに自身を投影して一体的つながりを実感できるかどうか、それが問われている。ゆえに、その結節点をつくるものが感情なのだ。
あるとかないとか、即物的に済ませられるならば、それは独立した存在感はあっても、紐づけによる広がりがない。自身と紐づかないものは、刹那的であって、持続性は期待できない。つまり、次をつくり出す駆動力、エンジンになるもののカギは感情領域にあるということだ。
一方、夏目氏が店を始めた背景にあるのは、「白T好きを増やしたい」というシンプルかつ、心からの願いだ。そこに「顧客はこんな商品を求めているだろう」という迎合の精神はない。
情報源: 「白T専門店」が示唆するアパレルの未来 (2ページ目):日経ビジネスオンライン
More from my site
 なぜモノベースではダメなのか 顧客はドリルが欲しいのではない、穴をあけたいのだ、といった認識の乖離の話は何度も聞かされている。ではなぜそうした事態が改まらないのか。
結局はコミュニケーションを前提としているか否かで大別できる話だろう。要するに「提供」と称して受け渡してクロージングだとみなすか、それとも提供の先にある相手の行動までキャッチアップしているか。
別の観点からいえば、不特定多数の顧客を […]
なぜモノベースではダメなのか 顧客はドリルが欲しいのではない、穴をあけたいのだ、といった認識の乖離の話は何度も聞かされている。ではなぜそうした事態が改まらないのか。
結局はコミュニケーションを前提としているか否かで大別できる話だろう。要するに「提供」と称して受け渡してクロージングだとみなすか、それとも提供の先にある相手の行動までキャッチアップしているか。
別の観点からいえば、不特定多数の顧客を […] 自己創造能力が求められる 「環境と戦略と組織のダイナミックな適合」のもう一つの重要な面は、環境対応の主体者である組織自体が自らの環境適応の在り方を見出していかなければならないことです。�
これは自らが自己変革、自己創造を見出す能力といえます。
�H.I.アンゾフは、アルフレッド・チャンドラーの「組織は戦略に従う」に対応して、「戦略は組織に従う」としました。
これは環境適応する戦略創造と戦略実 […]
自己創造能力が求められる 「環境と戦略と組織のダイナミックな適合」のもう一つの重要な面は、環境対応の主体者である組織自体が自らの環境適応の在り方を見出していかなければならないことです。�
これは自らが自己変革、自己創造を見出す能力といえます。
�H.I.アンゾフは、アルフレッド・チャンドラーの「組織は戦略に従う」に対応して、「戦略は組織に従う」としました。
これは環境適応する戦略創造と戦略実 […]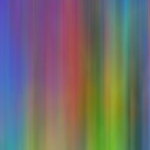 ストラテジック・エッジ 戦略水準としてみることのできる「安定的」「反応的」そして「先行的」、さらには「探究的」「創造的」の言葉は、環境適応を実現していくための「戦略の推進力」をとして理解していくことが重要といえます。
戦略水準1から3の「安定的」「反応的」「先行的」は、主として現在の事業領域を深耕しながら、さらに競争優位性を高めていくかが問われます。
これは「競争経営」の戦略概念がその中心と […]
ストラテジック・エッジ 戦略水準としてみることのできる「安定的」「反応的」そして「先行的」、さらには「探究的」「創造的」の言葉は、環境適応を実現していくための「戦略の推進力」をとして理解していくことが重要といえます。
戦略水準1から3の「安定的」「反応的」「先行的」は、主として現在の事業領域を深耕しながら、さらに競争優位性を高めていくかが問われます。
これは「競争経営」の戦略概念がその中心と […]